福岡大学の土木工学科は、今年の4月から名称が「社会デザイン工学科」に変更した。
廃棄物学会に所属しているので、廃棄物の視点からの木質資源の循環ということで、廃木材の有効利用と、活性炭について話したい。
この研究は、平成3年くらいから福岡市と共同で調査をはじめた。市内の廃棄物に木材系のものが増えてきたということがある。1960年後半から1970年代の建物が徐々に建替えに入ってきたことから、当時の清掃局からの依頼である。それと同時に、都市公園や天神界隈に木を植えたものが、剪定した樹木の廃棄物をどうリサイクル処理すかということもあった。
廃棄物の埋め立ての機能は、不要物の所蔵場所であり、福岡方式としての処理機能を持つ。埋立地は単なる穴でなく、分解と再生産する場所ということが一般化している。日本は埋め立てに適する場所が少ないため、焼却主体にやってきた。先進国で焼却を主体にしているのは日本だけである。
1970年以降、都市ごみの処理は80%近くは焼却しているので、焼却灰の重金属やダイオキシンが注目され、現在に至っている。
木質廃棄物は、福岡市の場合、年間5〜6万トンある。その中で活性化覆土という木炭と活性炭の中間的なものが2万トンある。2万トンというと、一日、約50トン木材を焼却する量に相当する。それだけの量が福岡だけである。
我々が考えたのは、重金属や有害物質を埋立地の中で、吸着や分解することができないか考えた。ごみを埋立地に投下すると、覆土で覆うが、量的には全体の20〜30%になるので、この覆土に機能を持たすことができないかということに調査・研究を開始した。即ち、ごみの飛散を防ぐという従来の機能を持たせながら、吸着効果や有害物質の分解菌を覆土の中にストックすることを考え、木炭に注目した。木炭は炭化温度により機能が違うので、いくつかの温度で調べた。
福岡市の廃木材の不純物の混入割合は、表1のとおりである。この廃木材を、表2のとおり、300℃、600℃、900℃の3段階で炭化して、吸着特性を調べた。
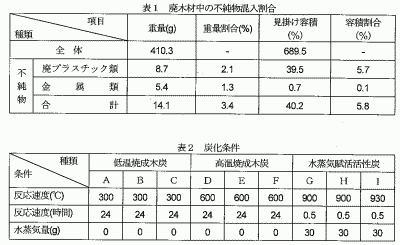
これを覆土に混入して、浄化できないか考えた。
即ち、重金属、有害物の吸着、有害物の微生物分解等ができないか4年間実験を行った。
その一端を紹介すると、建築廃材を集め、中部地区にあるロータリーキルン炉を借りて実験を行った。
吸着特性は、600℃で焼成したものは吸着性能がある。高温焼成木炭は、活性炭と木炭の中間程度で「活性化木炭」とネーミングした。吸着性能等は表のとおりである。
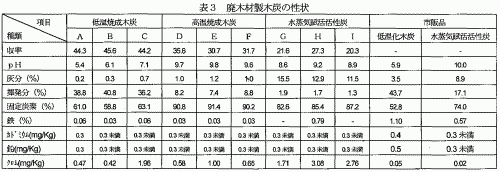
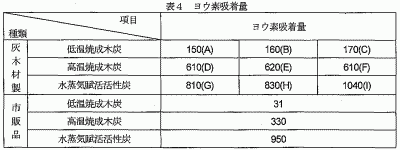
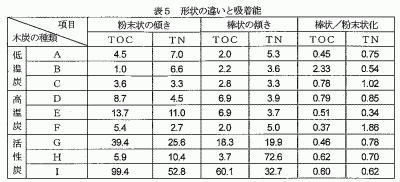
バッチテストで可能性が出たので、埋め立てを模擬した実験を行った。
我々が期待する廃木材を利用した将来の活性化覆土は、吸着やバイオリアクター、ABCアクション?の3つの機能を有する新しい覆土材である。
活性化覆土助剤として、普通の土の覆土よりも活性化木炭は、吸着性能、有害化学物質の分解等につていも効果があることがわかった。
まとめると以下の通りである。
- 廃木材を再利用する事によって焼却量を約10%削減できる。
- 廃木材を木炭化する事によって温室効果ガス(CO2)の発生を1−5%削減できる。
- 木炭化し、埋立地覆土材として再利用する事によって覆土量を約80%削減できる。
- 木炭類の粒度分布は悪く、覆土材として再利用する場合、現在覆土として使用されている山土との混合或いは含水率を上げる等の施工に際しての工夫が必要である。
- 廃木材製の木炭類には塗料中に含まれていた重金属類が残留しているものの、ほとんど溶出されない。
- 活性化木炭化及び活性炭化したものは臭気成分及び浸出水中の有機汚濁物質や重金属類の吸着能が高く、覆土材として再利用する事によって埋立地における種々の負荷の軽減が期待できる。
以上のように廃木材を木炭化し、覆土材として再利用する事によって埋立処分量の軽減並びに埋立地によって引き起こされる種々の環境負荷を軽減する事が可能であり、特に、活性化木炭化及び活性炭化が有効であることが示唆された。
今後は、各種木炭の埋立施工上の問題点を抽出し、検討する必要がある。更に、覆土材として木炭を利用した場合の、覆土層における微生物の挙動並びに特性を把握することにより、バイオフィルターとしての新たな覆土工法の開発も可能であり、今後大型埋立模型槽を用いた継続実験並びに現場における覆土助材としての施工実験等が重要であると考えられる。
我々のグループは埋立地を単なるゴミ捨て場としてではなく、人間の体に例えている。ポンプは心臓に相当し、臓器は解毒、腎臓がフィルターとすると、活性化木炭を用いたものは臓器移植に相当する。
木材を最終的に炭酸ガスと水にするのはさびしいと思われるかもしれないが、埋立地の中に素晴らしい木質が遺伝子を持った形であるので、この分野にも関心を持ってほしい。
日本有機性資源協会(JORA)が3年前に設立され、その中に木質系の分科会が設立された。大手建設業界の木質関係者からなる委員と寺沢と有馬先生とで情報を整理してきた。まず、JORAでの活動を紹介したい。
JORAの木質分科会では、木質廃棄物(木屑)を、建設発生木材(新築系、解体系)、剪定材、間伐材、流木材、バーック材などと分類し、その年間総発生量を1,000万トンと推定した。
建設発生木材は、年間約500万tで、その内の250万tが土木・建築系(新築系)である。これらは自ら利用の形で利用が進められている。解体・改装工事系(解体系)の廃材も同じく250万tである。これらはチップにして燃料として利用されているが、その多くは、縮減(焼却・埋立)の対象であった。バーク材が400万tである。剪定木材は調査中で、きちっとした数量が出ていない。間伐木も山で眠っているものは資源であると認識されているので、廃棄物としての数量が出ていない。
木質廃棄物の実際の処理方法は、まず、リサイクルステーション(木屑の中間処理施設)への搬入と処理施設でのチップ化である。基本的に中間処理施設が少ない状況であり、建設現場から半径50km以内に、その中間処理施設がない場合は、縮減してもよいということになっている。そのため、木屑の多くが縮減対象であった。昨年12月に焼却炉のからのダイオキシン排出濃度の規制が強化され、ほとんどの炉で焼却処理が難しくなった。一方、埋め立て地も残り少なくなってきている。解体系の木屑の処理をどうするか、また、有効利用の促進をどう進めるかは、業界での最優先課題となっている。
現状では、木屑の38%しか再利用されておらず、62%は縮減(焼却や埋立)されている。2010年までに、縮減等は発生量の10%まで下げることが法的に義務付けている。
再利用の内容は、マテリアルリサイクルとして、燃料用チップ、製紙用チップ、堆肥用資材、炭化用、再生ボード用などである。その再利用量は決して多くはない。木屑の再利用が阻害されている原因は、第1に中間処理施設での破砕の行為の目的が不明確である事に一部起因している。すなわち、作られたチップが、ボード用なのか、燃料用なのか、あるいは焼却・埋立処理用なのかが、はっきりしない。闇雲にチップ化されており、その結果、チップのサイズが不揃いであり、異物の除去が不徹底である。リサイクル加工業者側から見ると、安心して使えない。
第2に、木屑の中間処理場は全国175箇所あるが、圧倒的に数が足りない。建設現場から半径50km以内に施設がある場合は限られる。従って、多くの木屑は縮減(焼却・埋立)に回ってしまっていた。
木屑流通阻害の原因の3番目は、木屑の新用途開発があまり進んでいないことである。新用途の候補は、(1)木屑とプラスチックの複合化ボード(エンジニアリングウッド)、(2)解体良質部材の集成材として再利用、(3)木質の加水分解・エタノール醗酵(エチレン)、(4)炭化物の高付加価値化(電磁波遮へいボード)、(5)バイオマス発電(木屑の大口需要)などがある。バイオマス発電の場合、燃材確保の問題があり、その規模をどうするかなど、長期的展望にたった問題解決が重要である。
これらの阻害要因をなくすためには、(1)チップの公的規格づくり(これを早く作らないと、マテリアルリサイクルとしての方向性が見えない)、(2)リサイクル施設の増設(税の優遇、規制緩和、地方自治体などの公的関与が必要)、(3)再生製品指定制度の緩和(土木現場から出るバージン材への規制緩和)、(4)グリーン購入法の実行(再生製品の具体的購入促進)などが必要である。更に、(5)解体業者の分別解体(解体技術の向上)の促進、(6)解体を容易にする住宅用木質資材製造の技術革新の開発、(7)新用途開発のための技術革新の開発、などが必要である。この様に、木屑再利用を推進させるためには、規格作り、規制緩和、各種技術革新、新規需要開発などの多くのハードルが存在し、これら全てを同時にクリヤーする必要がある。実に前途多難である。
以上、JORAでの検討項目、問題点把握の状況を紹介した。
これまで述べたように、木質材料だけを使ってリサイクルしようとしてもかなり難しい現状がある。他に方法は無いものだろうか。そこで、木屑と他のバイオマス廃棄物とを複合的に処理する方法を提案したい。
木屑という難分解性の廃棄物を(A)とし、生ごみ・屎尿・家畜糞尿など、腐臭や汚臭を発生しやすい易分解性廃棄物を(B)とする。ともに、困りもののバイオマス廃棄物である。(A)も(B)も発生する業種が違うこともあって、それぞれ単独に処理されている。発想を転換して、(A)と(B)とをそれぞれ単独に処理するのではなく、複合処理するシステムを導入してはどうか。一定量の(A)中に(B)を連続的に長期間投入し間歇的に攪拌する。すると、(B)は(A)の中で無臭の内に分解し、消滅する。最終的には、有機肥料・土壌改良材としての資源に変換する。このことは、演者らによって、すでに実証されている。
平成11年に、「家畜排せつ物の管理の適正化および利用の促進に関する法律」が施行され、ビジネスチャンス到来と捉える事の出来る状況になった。北海道では120万頭の家畜が飼育されている。乳牛1頭で、人間の40-50人分くらいに相当する糞尿を排出する。従って、乳牛120万頭では、5〜6千万人相当の糞尿が排出されている計算になる。これらは、これまで適正に処理されず、垂れ流し状態であった。この最悪な状況の改善のために施行された法律である。糞尿の地下浸透を防止するために堆肥盤としてコンクリート敷くこと、雨に流されないように堆肥盤の上に屋根をつけること、などを義務づけている。はたして、この法律1本で、家畜糞尿問題は解決するのであろうか?
他方、300〜400m3のオガ屑を使うことで、80頭を飼育していた酪農家の排出する糞尿を消すことに成功した。これまでに総計2,500t〜3,000tの乳牛の糞尿が、オガ屑の中で臭いもなく消えた。オガ屑中には窒素、燐酸、カリが蓄積し、立派な濃厚有機肥料が出来上がってしまった。最初に投入したオガ屑は交換することなく、すでに連続使用3年目に入っている。この様な状況になったのは、従来法のように堆肥作りが目的ではなく、糞尿を消すことが優先した目的があるからである。
道内12,000軒の酪農家が、本法を採用すると、森林資源の需要が大幅に増大する。日本全体の家畜糞尿処理を仮に本法で実行すると想定すると、年間の木屑発生量のほとんどが利用されるであろう。
さて、基本に戻って、オガ屑の特性について述べさせていただく。
1)オガ屑は、セルロース、ヘミセルロース、リグニンなどのからなっており、炭素、水素、酸素を主体とした有機性材料である。窒素、燐、カリウムなどの無機質はほとんど含まれていない。生ゴミ分解装置中で、オガ屑をマトリックスとして用い、装置を稼動させる。一定量の生ごみを数ヶ月間、装置に連続投入する。生ゴミ中の有機物は、炭酸ガスと水とに分解し、フミン質が一部残る。この間に、生ゴミ由来の無機質がオガ屑中に蓄積される。従って、使用済みのオガ屑を施肥すると、蓄積した無機質が肥料としての効果を発揮する。
2)オガ屑は、その粒子の大きさが変わっても(極微少部分を除く)空隙入水量すなわち空隙率が15〜20%と大きく変わらない。すなわち、一定容量のオガ屑は、その85〜80%が空隙なのである。保水量も40〜30%と大きく変わらない。従って、空気保持能も55〜40%と大きく変わらない。オガ屑は、適度の水分を保持しつつ十分な空気を保持することの出来る特殊なマトリックスである。この性質は、団粒構造を有する農耕土壌に類似する性質であり、好気的条件下で好気性微生物が活躍する環境を提供する。この性質は、家畜糞尿の処理のみでなく、いろいろなバイオマス廃棄物処理の場面で利用される。
3)オガ屑は、比表面積が大きいため、その表面から水分が効率よく蒸発する。この水分の蒸発は、オガ屑のマトリックスを好気的条件に保持することに貢献する。バイオトイレはじめオガ屑を利用した各種システムは、悪臭を発揮する事無く屎尿を濃縮し、資源化する。言い換えると、これらの各種システムは、いずれも効率の良い水分蒸発装置である。
バオトイレは、富士山での2年にわたる公開試験に耐え、その実用性が証明された。山岳用のみならず、身障者用、工事現場用、イベント用、室内介護用などその種類も多い。水を使わない、臭いがしない、生ゴミも処理できるトイレとして好評である。また、バイオトイレは災害時に特に威力を発揮する。各地で、バイオトイレの使用および備蓄を考慮し始めている。
ここで、バイオトイレが何故臭わないかを説明したい。
屎尿はその90%強が水分であり、水分を蒸発させると生物分解させる必要のある有機性固形分は、たかだか10%弱である。先にも述べたが、臭いを発生させることなく屎尿を濃縮させれば、屎尿の処理は難しくない(濃縮資源化)。1人が1日に50〜60リットルもの飲料水を使用する現行の水洗トイレ(希釈・廃棄)は、そろそろ考え直す時期に来ている。さて、混合した屎尿から発生する強力な臭気は、尿中に存在する尿素に由来する。尿素は、嫌気的条件にあって、嫌気性バクテリアの生産するウリアーゼに接触すると、効率よく炭酸ガスとアンモニアに変換する。このために強力な臭気(アンモニア)が発生する。従って、屎尿は、嫌気性バクテリアが活動する環境におかなければ、アンモニアを発生せず、従って臭気も発生しない。
屎尿をオガ屑の中に投入・混合すると、尿の水分ははオガ屑の空隙に吸収・分散し、もはや液体状態では無くなる。尿中の有機物である尿素はオガ屑の表面にフィルム状に露出し、好気的条件下で好気的バクテリアにより分解される。嫌気的ではない条件下では当然ながら嫌気性バクテリアは活動せず、アンモニアは発生しない。従って臭気の発生はない。
他方、オガ屑の緩衝能力の高さも、アンモニア揮散阻止の重要な要因でもあるが、詳細は割愛する。
易分解性のバイオマス廃棄物(B)と難分解性の木屑(A)を複合処理して出来上がったコンポストは、「特殊コンポスト」である。有機肥料としても、土壌改良材としても有効である。また、この特殊コンポストは、ペレット、植林用ポット、難燃ボードなどへと成型・加工すれば、農用、土木用、工業用の他機能性資材へと変換し、より広く利用することが可能である。
以上、オガ利用の特色とその新規利用の具体的方法について述べた。
木屑を使った新しいシステムが動き出すことに期待したい。日本は、食糧、木材、石油など海外からの輸入に頼っている。食糧と木材は、海外の生産地の土壌栄養分を含む。それらのコンポスト化は可能である。しかし、日本国内の農地で全てを消費することは理論的にも無理がある。では、どうするか。地域内循環を進めるとともに、地球内循環を考慮すべきである。食糧、木材など海外から来たバイオマス資源の廃棄物を元に作られたコンポストは、海外のバイオマス生産現場に戻すと言う地球規模の大きな循環を考える発想が必要である。肥料を必要としている農民は世界的にいっても多いのであるから。
![]() 保存
>
保存
>![]() お気に入りへ
>
お気に入りへ
>![]() 印刷
印刷